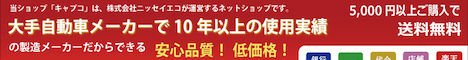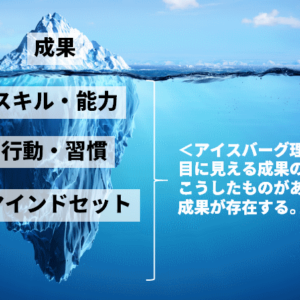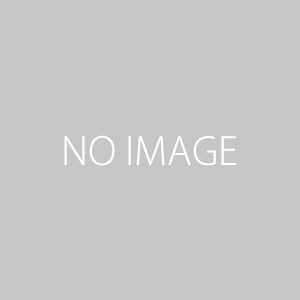情報オーバーロード
滋賀出張に車で行くと必ず通るのが高速道路。そして車で移動していれば巻き込まれるのが渋滞。滋賀から神奈川に帰る道中、たいてい名神、新東名、東名ルートで戻っています。先日新東名も後半に差し掛かりそろそろ東名だぁって時に、急に御殿場の先で事故による渋滞の情報が出てきました。3km 10分、まぁ大したことないかと走っていると、30分、100分、150分、180分、しまいには東京まで不明の表示。これはまずいと同乗していた妻に調べてもらうと、9台の玉突き事故で6台が自走不能らしいよとのこと。そして日曜日の夕方で行楽帰りの車も多い時刻。Google MAPを活用し、御殿場で降りて次のIC乗れという指示で従い、降りて次のICを目指すとIC入口が渋滞でピタッと止まってしまう。多分みんな検索し同じルートを取ったのでしょう。そうこうしていると対向車線から、東京、神奈川ナンバーが続々と降りてくる状態。ここは無理だと迂回し246ルートに変更。ここでも246に入るまでに渋滞で止まってしまう。Google MAP、Yahoo 地図、Apple Mapで検索するも、どのルート通っても3時間越え。関東平野に入る東名、246、箱根ルートが全て渋滞表示、超迂回ルートの中央道を調べても真っ赤。これはどこもだめだと諦め、そのまま246で帰宅。いつもより2時間オーバーでの帰宅となりました。
手元のスマホでなんでも検索できる時代で、すぐに全国の渋滞状況がわかります。車1台につき1検索ではなく、複数の人が乗っていればみんなで検索です。あの渋滞中、どれだけの情報通信が飛び交っていたのでしょうか。想像を絶すると思います。
現代では、1日に接する情報量は江戸時代の1年分、平安時代の一生分と言われています。入ってきた情報は脳ではどんな情報でも一つ一つ判断を下し処理していくので、脳が疲れてくるそうです。現代人は非常に多い情報を判断しなければなりません。まだ正しい情報なのか間違った情報なのかの境目も曖昧な情報も溢れており、結局最終的な情報に辿り着けない場合も出てきます。この先の情報量の増加は2021年から2030年には30倍、2050年までには4,000倍になるとの見込みです。この先、情報が溢れる時代、どのようにして必要な情報を取得していくかが大きな鍵となってくるでしょう。江戸時代の1日を体験してみたいものです。